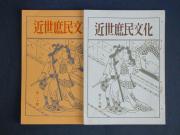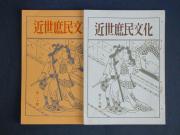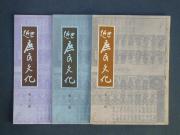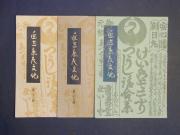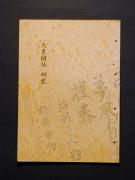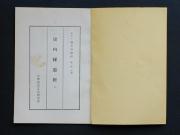閑話究題 XX文学の館 珍書屋 戦後の研究会 近世庶民文化
十九号 ~ 二十六号、増刊号
「元禄文學資料」
「大東閨語」研究
「房内秘道経」
| 十九号、二十号 |
|---|
| 頁数 | 刊年 |
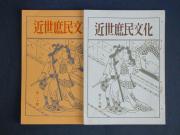 |
|---|
| 19 | 32頁 | 昭和二十八年十月五日 |
|---|
| 20 | 56頁 | 昭和二十八年十二月十五日 |
|---|
十九号(資料特集号)
| 目次 | 表紙裏 |
| 花勝美色結綿(写真凸版) |
解題)花咲一男 | 1 |
| 女大樂寳開(一部写真凸版) |
解題)岡田 甫 | 7 |
| 茶室 | 32 |
| 後記 | 裏表紙 |
当号に執筆している離離庵戯州は山路閑古の別号である。この後も觀雲亭の号で寄稿している。
二十号
| 目次 | 表紙裏 |
| 黒澤翁満の「酒席醉話」(1) |
關野月影 | 1 |
| へきれき漫筆(8) |
魔山人 | 5 |
| 春畫歌 | 8下囲 |
| 謎々「黑船祭」 |
荒木野要太 | 9 |
| 四十八襞考 |
離離庵戯州 | 12 |
| ほどの繪 | 15下囲 |
| 註解「論御」(2) |
伏見沖敬 | 16 |
| つじうらどゝいつ |
きさら | 22 |
| 「眞似鐵砲」の編者に就いて |
高林秋之介 | 26 |
| 明和版「如意君傳」其他 |
向臺樓人 | 27 |
| 「末摘花註解」を讀んで |
西村富夫 | 29 |
| 「水の行末」の大阪語 |
上田鹿園 | 30 |
| 並べ百員詳釋(9) |
山路閑古 | 33 |
| 狂詩片々 | 37下囲 |
| 〔資料室〕花勝美色結綿(中之巻)(写真凸版) | 38 |
| 「註解」「定本」の再刊 |
岡田 甫 | 42 |
| 〔資料室〕正直咄大鑑(黑之巻) | 43 |
| 茶室 | 53 |
| 質疑應答 | 56 |
| 後記 | 裏表紙裏 |
| 二十一号 ~ 二十三号 |
|---|
| 頁数 | 刊年 |
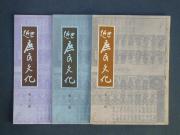 |
|---|
| 21 | 64頁 | 昭和二十九年二月二十五日 |
|---|
| 22 | 56頁 | 昭和二十九年四月三十日 |
|---|
| 23 | 56頁 | 昭和二十九年七月五日 |
|---|
笠野馬太郎(長谷川卓也氏)の『風俗出版物總目録』と次号の『績』は江戸文芸とは関係ない現代の地下出版、公刊発禁本のリストであるが、当時としては画期的な程の数を取り上げている。
二十一号
| 目次 | 表紙裏 |
| 幕末諷刺文學の一節 |
齋藤昌三 | 1 |
| 「未摘花」四篇の編者(1) |
山澤英雄 | 5 |
| ぬるかのむか長命丸 |
魔山人 | 8 |
| 昭和の末摘花 |
秦 豊吉 | 12 |
| 風流狂歌選 | 12下段 |
| 「顔」などの事 |
尾崎久彌 | 14 |
| 黒澤翁満の「酒席醉話」(2) |
関野月影 | 19 |
| 養生歌 |
岡田 甫 | 23 |
| 風俗語あれこれ(3)
|
花咲一男 | 26 |
| 「定本末摘花」補訂 | 30下段 |
| 註解「論御」(3) |
伏見冲敬 | 32 |
| 周作人と川柳 |
岡田 甫 | 37下囲 |
| 好笑大津繪節(2) |
きさら | 38 |
| 枝垂柳抄 | 38下段 |
| 並べ百員詳釋(10) |
山路閑古 | 40 |
| 「かわかし」に就いて |
西村富夫 | 42下囲 |
| 川柳地黄丸 |
未知庵主人 | 43 |
| 讀造化機論 | 50下囲 |
| 風俗出版物總目録
|
笠野馬太郎 | 51 |
| 第一回大會開催 | 63左 |
| 質疑應答 | 64 |
| 茶室 | 65 |
| 後記 | 裏表紙 |
「近世庶民文化」発刊三周年の記念大会に関する記事が目を引く。出席者の顔ぶれからも会が順調に発展していることが窺える。
二十二号
| 目次 | 表紙裏 |
| 船いくさの巻 |
岡田 甫 | 1 |
| 「末摘花」四篇の編者(2) |
山澤英雄 | 13 |
| 「かわかし」その他 |
濱田桐舎 | 18下 |
| おいらんと飯盛 |
魔山人 | 19 |
| 忠臣藏ばれ句 |
きさら | 22 |
| 帆柱丸・蝋丸 |
未知庵主人 | 24 |
| 黄庵句會 | 29下 |
| 註解「論御」(4) |
伏見冲敬 | 30 |
| 手の窪漫筆 |
高林秋之介 | 34 |
| 「飛びもの」私見 |
采微庵 | 35下段 |
| 黒澤翁満の「酒席醉話」(3) |
關野月影 | 37 |
| 大會の寫眞について | 40下囲 |
| 枕檜 |
富士野鞍馬 | 41 |
| 大會句抄 | 44下囲 |
績取締られた風俗出版物
- 公刊出版物の部(つずき)
- 非公刊出版物の部(つずき)
|
笠野馬太郎 | 45 |
| 夜開く ――三周年祝賀大會記事―― |
觀雲亭 | 47 |
| 三周年祝賀大會(スナップ写真) | 別丁4頁 |
| 大會を終えて |
岡田生 | 51 |
| 大會スナップ | 51下段 |
| 〔資料室〕四季の姿見(写真凸版) | 53 |
| 茶室 | 56 |
「末摘花」以上のバレ句集、「柳の葉末」の輪講が開始される。
二十三号
| 目次 | 表紙裏 |
| 女悦丸 |
未知庵主人 | 1 |
| 夏閨枕 |
片岡光寛 | 6下 |
| まり唄十二月考(一) |
觀雲亭主人 | 7 |
| 武玉川の破禮句 |
魚澤白骨 | 13 |
| みだれかご(3) |
岡田 甫
| 14 |
| へきれき漫筆(9) |
魔山人 | 17 |
| 湯女 | 20下 |
| 「べに筆」補記(一) |
樂虚子 | 21 |
「柳の葉末」合同研究〔第一回〕
- 礎稿 岡田 甫
- 山路閑古・田中蘭子・高橋痩蛙
- 母袋未知庵・魔山人・橘菖莎庵
- 岡樂虚子・山澤碌々・濱田桐舎
- その他
| 24 |
| 茶室 | 54 |
| 痩蛙さんを惜む |
松 主水 | 56 |
| 未刊「柳多留」翻刻と基金募集 | 57 |
| 後記 | 裏表紙 |
当号には奥付がない。従って、刊行年月は推測である。また、「近世庶民文化」の文字もどこにもないので、この冊子単独では同誌の増刊号であることは判らない。
| 増刊6号「元禄文學資料」 |
|---|
| 頁数 | 刊年 |
 |
|---|
| 47頁 | 昭和二十九年八月(?) |
| 二十四号 ~ 二十六号 |
|---|
| 頁数 | 刊年 |
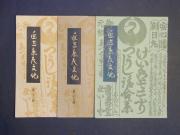 |
|---|
| 24 | 48頁 | 昭和二十九年九月十日 |
|---|
| 25 | 48頁 | 昭和二十九年十一月十五日 |
|---|
| 26 | 56頁 | 昭和二十九年十二月三十日 |
|---|
二十四号
| 目次 | 表紙裏 |
| 手のくぼ考 |
岡田 甫 | 1 |
| 「弦曲粹辯當」伏字考 |
鈴木倉之助 | 9 |
| おちはがき |
魔山人 | 14 |
| 長歌(宿屋飯盛) | 19下 |
| 『川柳江戸軟派』のことなど |
佐々木一郎 | 20 |
| 取消とお詫び、維持会員名簿 | 22下 |
| まり唄十二月考(二) |
觀雲亭主人 | 23 |
| 未刊「柳多留」翻刻 | 29下囲 |
| 「べに筆」補記(二) |
樂虚子 | 30 |
| 編集室から | 33左 |
| 「柳の菓末」合同研究〔第二回〕 | 34 |
| 茶室 | 47 |
二十五号
| 目次 | 表紙裏 |
| 折口先生の珍文献 |
水木直箭 | 1 |
| 「瓦版のはやり唄」伏字考 |
林 頼介 | 6 |
相模下女診斷
- 相模下女は好色なりということ
- 下女に相模産多かりしこと
- 下女は大もてなりしこと
- 相模下女は世襲たりしこと
- 正体みたり枯尾花ということ
|
岡田 甫 | 11 |
| まり唄十二月の原歌 |
愛日樓閑々 | 18 |
| まり唄について |
上田鹿園 | 18下 |
| 白ちり |
日野光雄 | 19下 |
| あの頃のこと |
温故書屋主人 | 20 |
| 「未刊柳多留」について | 23下 |
| まり唄十二月考(三) |
觀雲亭主人 | 24 |
| 「べに筆」補記(三) |
樂虚子 | 29 |
| 『註解』ざんげ話 |
岡田 甫 | 32下 |
| 「柳の葉末」合同研究〔第三回〕 | 33 |
| 「葉末研究」異見(諸家) | 46 |
| 茶室 | 47 |
| 後記 | 裏表紙 |
二十六号
| 目次 | 表紙裏 |
| 大東閨語雜考 |
廣田魔山人 | 1 |
| 春臠柝甲の作者は誰 |
齋藤昌三 | 17 |
| 川柳長命丸 |
未知庵主人 | 21 |
| 三疊樣 |
田中蘭子 | 30下 |
| 雜俳吐溜抄 |
松平五面子 | 31 |
| 三圍の鳥居 |
稲垣武雄 | 32下 |
| 別冊「川柳吉原志」(一) |
樂虚子 | 33 |
| まり唄十二月考(四) |
觀雲亭主人 | 39 |
| 「柳の葉末」合同研究〔第四回〕 | 47 |
| 茶室 | 56 |
| 後記 | 裏表紙 |
| 増刊7号「大東閨語」研究 |
|---|
| 頁数 | 刊年 |
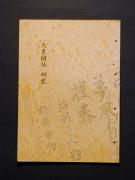 |
|---|
| 39頁 | 昭和二十九年十月十一日 |
| 大東閨語考 |
竹柏野葉三 | 1 |
| 註譯 大東閨語 |
伏見冲敬 | 9 |
失われてしまった中国の性典原本を本邦の医学書「医心方」(丹波康頼)『第二十八房内』の記述から抜粋、復元を試みた労作である。
尚、この号にも奥付は無く、「近世庶民文化研究所」とあるのみなので、刊年は推定である。
| 増刊8号「房内秘道経」 |
|---|
| 頁数 | 刊年 |

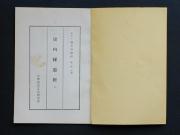
|
|---|
| 56頁 | 昭和三十年三月(?) |
| 内容 | 2 |
| 「房内秘道經」に就いて |
稲井 豊 | 3 |
- 彭祖經
- 素女經
- 素女方
- 玄女經
- 洞玄子
- 玉房秘訣
- 玉房指要
- 仙經
|
| 5 |